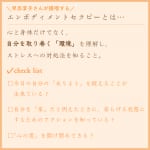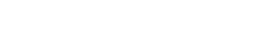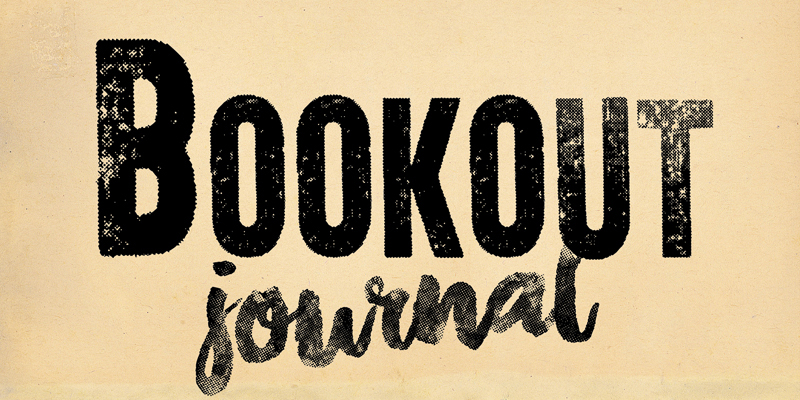
【インタビュー】激動の時代に、最も大切な“ニュートラリティー”とは? セラピスト早志享子さん【後編】
BOOKOUTジャーナルとは
知られざる想いを知る―。
いまいちばん会いたい人に、
いちばん聞きたいことを聞く、
ヒューマンインタビュー。
撮影/長谷川 梓
文/井尾 淳子

日本初のアメリカンポラリティセラピー協会認定プログラムディレクター、講師、また日本ポラリティセラピーサポート協会会長を務める早志享子さん。
ポラリティセラピーとは、エネルギーの流れを整え、心身のバランスの回復を目的としたアメリカ発祥のホリスティック療法です。後編では、早志さんの人生の大きな転機となったポラリティセラピーで学んだこと、また、激動の時代をサバイブする心のありよう、“ニュートラリティー”について、詳しくお話を伺いました。
*前編は、こちら(https://www.wanibookout.com/123648/)。
人間関係においても“ニュートラリティー”で問題解決がスムーズに
──前編では、“ニュートラリティ―”という心のありようによって、「今、自分はどうすればよいのか」などの優先順位が明確になり、問題解決能力が高まるなど、ベネフィットを得られるというお話を伺いました。それは人間関係においても同様に、問題解決がスムーズになるのでしょうか。
人間関係でいえば、「自分と他者の境界線が明確になり、依存や自己犠牲に悩まされることがなくなる」「他者にマウンティングを取られることなく、自分で思考するスペースをしっかりと保つことができる」「過去のトラウマティックな出来事を、新たな視点と体験で上書きすることができる」「自分と他者を比べる必要がなくなる」…などですね。
例えば、「こんなひどい上司がいる会社は辞めるしかない」「こんな夫とは離婚するしかない」という悩みも、極端な決めつけをせずに、別の角度からの選択肢、解決策が見えてくる。「同僚を味方につけて、新しいプロジェクトを立ち上げることに挑戦したら、上司のことはまったく気にならなくなった」「自分がやりたかった仕事を大事にするようにしたら、いつのまにか夫が家事や子育てに協力的になった」など。
新しいバランス、新しい調和、新しい自由さを選び取ると、実は、問題は問題ではなくなるんです。これからの時代は特に、ニュートラリティーという便利な視点をもつことで生きやすくなり、しがらみからも解放されて、人生は楽になると思います。
自分に興味津々になる、という態度
──コロナ禍を境に、社会の価値観は大きく変わりました。以前は「会社に行くのが当たり前」だったのに、オンラインでの働き方が浸透するなど、様々なジャンルでも制度やルールは大きく変わっています。そんな変化の大きい激動の時代においては、このニュートラリティーが心のお守りになりそうですね!
物の値段が急に上がったり、気候変動も捉え方が変わったり、情報の移り変わりがとにかく激しくなっていますよね。この現代社会では、固定観念にとらわれすぎると、変化についていけなくなってしまいます。でもこれまでの日本は、マインドセットすることで、心の安定を得ようとしてきました。以前は、「この会社にいれば安心」「安定収入があれば安心」という考え方がありましたが、それが崩れてしまいました。今はその前提がますます崩れて、何が「大丈夫」なのか、多くの人が分からなくなっている。それでも人は安心感を求める習性があるので、何かしらの「確かなもの」を探そうとする。でも変化が速すぎて、それすら見つけにくい。環境の変化が激しい時代は、それ自体がストレスになります。
──たしかに現代社会では多くの人が忙しく、ストレスまみれです。「自分が何を大切にしたいと感じているのか」ということ自体を見失いがちですが、そんなときはどうすればいいでしょうか?
自分は何を大切にしていたいのか。それがわからなくなったときに必要なことは、「自分自身に興味津々な態度を持つ」ということです。どんな感情や思考が浮かんできても否定せずに、「自分はこんなことを感じているんだ」と、自分を観察するようなまなざしを持つ。また、「自分に興味を持てている」ということは、とても大きな可能性を引き出します。それには限界がなく、開かれている状態だからです。
一方、決め付けや思い込みという制限がかかると、その時点で自分らしいエッセンス(その人にとって欠かせない、大切で必要な要素)から遠ざかってしまい、私たちはやがて「恐れをベースとした思考」に絡め取られてしまいます。
例えば、仕事や人間関係などで、「私って、こんなに傷ついていたのか」ということを興味津々に眺めてあげる。すると、「これはちょっと、何を置いても、自分を助けてあげなきゃいけないな」と、自分に対して客観的な処方箋を向けてあげることができますよね。つまり、それが心のゆとりにつながる。
「人は忙しすぎると心を見失う」とはよくいわれますが、そうなると自分が傷ついているにもかかわらず、「置いていかれる!」「切り捨てられる!」という恐怖心に襲われます。本当は、傷やケガを治してあげることが最優先なのに、「今はそんなことより、がんばり続けないと!」「この生活が維持できない!」などと思い込み、ずっとエンジンを吹かし続けてしまう。でもそれは、無意識に自分の中に取り込んでしまった、社会の仕組みに飲み込まれているだけなので、その構造にぜひ気づいていただきたいと思います。

「隠れた忠誠心」というトラップに気づく
──では、そんな思い込みに気づくためにはどうしたらいいでしょうか? 私たちは、自分でも意図せずに作り上げた思考の中で、ただもがいている気がしてきました。
私が主宰するスクールに、心のケアのプロフェッショナルクラスがあります。そこでとても興味深いなと感じたことの一つが、人は無意識のうちに、自分に対してさまざまな言葉をかけているということです。トイレに入ったとき、洗濯をしているとき、歯を磨いているときなど、何気ない日常の中で、ふと頭の中に浮かぶ言葉があります。これが「無自覚の思考」と呼ばれるもので、「ちゃんとしなきゃ!」とか「早くやらなくちゃ!」と自分を追い込んでいたり、必要以上にプレッシャーをかけていたりすることがあるんです。まさしく「自分が意図せずに作り上げた思考」で、「自分が本当に大切にしたいこと」と、「社会的、あるいは身近な家族の影響で、勝手に大事と思い込んでいること」が混ざってしまっている状態なんですね。
私の主宰するセラピースクールでは、「ファミリー・コンステレーション・セラピー※」というグループワークを学びますが、後者の方の思考(社会的、あるいは身近な家族の影響からの思い込みがある状態) のことを、「隠れた(見えない)忠誠心」といいます。
それは、自分から発動した気持ちでもなければ、生み出した価値観でもない、ただその場所で生きていくために植え付けられた文化のようなもの。いわゆる「外付けハードディスク」です。
例えば、「親には尽くさなければならない」とか「女性は男性を立てなくてはならない」とか。その背景には、子どもの頃にお母さんの悩み相談、愚痴の聞き役にされていたり、お父さんの顔色を伺っていい子を演じ、気を使っていたり…。そういう時期が長かった人は、子どもらしい感情を育てる時間を失って、頭では考えてないけれども、「両親よりも自分は成功してはいけない、幸せになってはいけない」という、隠れた忠誠心が根っこに植え付けられているんです。本心とは裏腹に、その思い込みを優先し、行動してしまうという隠れた忠誠心は、確実に「ニュートラリティーを阻害する、大きなトラップ」になりえます。
(※)ドイツの心理療法家ベルン・ヘリンガーが提唱したセラピーの手法。家族や先祖から受け継がれた無意識のパターンを明らかにし、心の問題や生きづらさの解決を目指す。ヨーロッパ、南米、メキシコでは高く評価されているが、Netflixのドラマシリーズ 「出会えていないもう一人の私に(原題:Another Self )」にて取り上げられるなど、アメリカでも注目されはじめている。
──特に介護の場面などでは、大いに起こり得ることですね。自分の心の中に、いつのまにか根付いた、自分をおろそかにする忠誠心はないか。そういうまなざしを向けるだけでも変われるでしょうか?
とても大事です。「もしかすると、自分は自分を大事にしていなかったのかも」「自分の心には、こんなパターンがあったのかも」と気づくだけで、心の円のかたちはどんどん広く、深くなっていきます。「自分にとって大切なものは何か」を見つめる眼差しも育まれて、今度はそれが心の中心点になる。すると、ニュートラリティーはおのずと保たれていくので、「自分を大事にしないことは、結果的には他者も周りも大事にしない状況に陥る」という、本来の構造全体が見えてきます。そのときようやく、悩みは悩みでなくなって、「その問題は、はじめから問題ではなかった」というプロセスをたどることができるのです。
*早志さんにはPodcast番組「ライフスタイルセラピー」にもご出演いただきました!
放送はApple Podcast、Spotifyなどの各音声配信メディアの他、BOOKOUTでもご視聴いただけます。第1回目はこちら(https://www.wanibookout.com/122024/)から。
早志 享子(はやし・きょうこ)
Enbodiement Therapy Institute 代表/ ディレクター (株)OneRoots 代表 Japan Polarity Therapy Foundation 代表 Primitive Ranch 夙川 代表 Polarity Therapy RPE,BCPP
 20 年のキャリアをもつセラピスト、プラクティショナー。米自然療法医師ランドルフ・ストーン博士(1890〜1981)が開発したホリスティック療 法「ポラリティセラピー」と、脳神経を守る「脳脊髄液」分泌液の流れを調整する手技 療法「クラニオセイクラルセラピー」という、2つの手技を独自に体系づけて活動。無意識の、深い根本部分に眠る心身の不調にアプローチするセッションは、クライアント からの信頼も厚い。講師として教えながら、海外講師のワークショップのオーガナイズや通訳、海外 でのワークショップなどを行う「エンボディメントセラピーインスティテュート」主宰。
20 年のキャリアをもつセラピスト、プラクティショナー。米自然療法医師ランドルフ・ストーン博士(1890〜1981)が開発したホリスティック療 法「ポラリティセラピー」と、脳神経を守る「脳脊髄液」分泌液の流れを調整する手技 療法「クラニオセイクラルセラピー」という、2つの手技を独自に体系づけて活動。無意識の、深い根本部分に眠る心身の不調にアプローチするセッションは、クライアント からの信頼も厚い。講師として教えながら、海外講師のワークショップのオーガナイズや通訳、海外 でのワークショップなどを行う「エンボディメントセラピーインスティテュート」主宰。
公式サイト https://embodiment-therapy.life