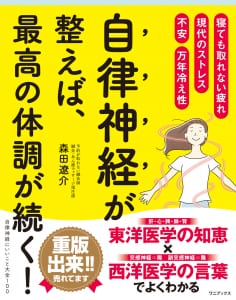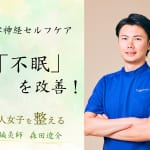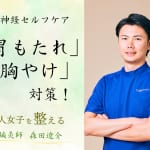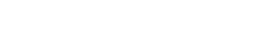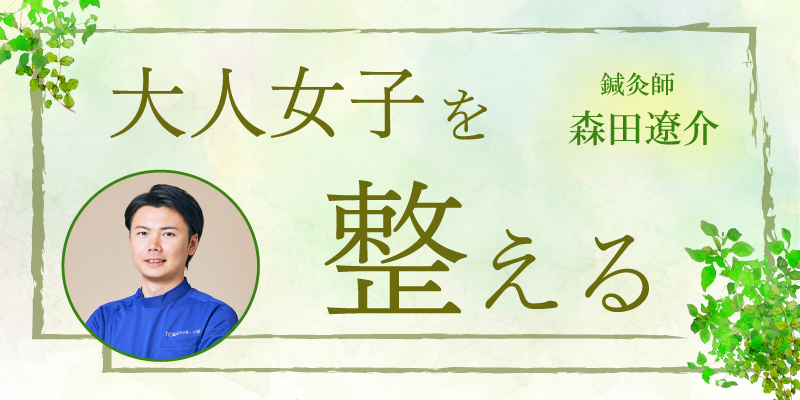
【自律神経セルフケア】「体質診断」であなたにぴったりなケアが見つかる!【東洋医学の気虚・血虚とは?】
「気虚タイプ」の不調と、その改善法

気虚(ききょ)は、エネルギー不足タイプです。気(き)・血(けつ)・水(すい/津液)を吸収することが苦手なタイプといえます。
更年期における気虚は、エネルギーの根本である「気」が不足した状態を指します。更年期のホルモンバランスの変化や加齢により、特に現れやすい症状の一つです。
気虚は体全体の機能低下を引き起こし、さまざまな不調に繋がります。とにかくエネルギーが足りないため、シンプルに「無理に頑張らないこと」を心がけて、体質改善を優先させましょう。特に、五臓の脾(ひ)という消化器機能の働きが重要になります。
気虚タイプのよくある日常
起きることが苦手で朝の時間経過スピードが特に早く感じる
↓
午前中の動きは悪くないが、昼食後にとても眠くなる
↓
寒がりでスーパーや美容院が苦手
↓
一度の食事で多く食べられないため間食しがち
↓
夕方には疲れ切ってしまい、力が抜けていく感じがする
↓
晩ご飯を作る気力もお風呂に入る気力も起きない

(イメージ:写真AC)
気虚とは
中医学で「気」は、生命エネルギーの源であり、全身を巡りながら以下のような役割を果たします。
・身体を動かす原動力
・体温や臓器の働きの調整
・血液(血)や体液(水:津液)を循環させる
・体のバリア機能を果たし、免疫機能を維持
更年期では、卵巣機能の低下やストレスの影響で「気」が十分に生成されなくなり、その不足が「気虚」という状態を引き起こします。
気虚の対策方法
(1)生活習慣の改善
・十分な休息をとる
慢性的な疲労は疲れていること自体を自覚しにくくなるため、意識して過労を避け、早寝早起を心がけましょう。みぞおちとヘソの間を温めて寝ると◎。
・食事の仕方を変える
暴飲暴食を控え、腹八分目を意識してください。早食いにも注意して。
・無理のない運動
ヨガや太極拳など、体力を消耗しない程度の運動で気の流れを促しましょう。
・ストレス管理
リラクゼーション法(瞑想やアロマセラピー)を取り入れてみましょう。
(2)食事による改善
気虚には「補気(気を補う)」効果のある食材をバランス良く、積極的に食事の中へ取り入れると良いでしょう。気(エネルギー)が不足すると体が疲れやすく元気が出ません。
おすすめの食材
・米、もち米、山芋、大豆:脾胃(消化器系)を強化し、気を補う作用があります。
・かぼちゃ、さつまいも:甘味があり、脾胃を温め、エネルギーを補給します。
・なつめ、高麗人参:補気の代表的な食材で、全身の元気を底上げします。
・鶏肉、卵:体を温め、消化吸収を助けるタンパク質源として最適です。
避けたい食材
・体を冷やす生野菜や冷たい飲み物、アイスクリームなど
・消化に悪い脂っぽい料理や辛いもの
・ウーロン茶

(イメージ:写真AC)
気虚を放置した場合のリスク
気虚を長期化させると大変危険です。他の不調を引き起こしやすく、免疫力の低下や慢性疲労がさらに悪化し、栄養を十分に吸収できないため日常生活が困難になることもあります。早期の対応が重要なので、まずは胃腸の不調から見直していきましょう。
まとめ…「気虚タイプ」のあなたへ
気も血も水(津液)も全身に巡らせるためには、まずは胃腸で食物や水分を消化吸収し体内に取り込むことから始まります。
胃腸に負担をかけないように、ゆっくりとたくさん嚙みながらすぐに飲み込まない、しっかりとお腹が空いてグーっと鳴ってから食べる、夕食を軽めにすることを意識してみてください。
気虚の「体質改善」をすることができなければ何も始まらないといっても過言ではないほど、重要なポイントです。
(「血虚」タイプは次のページへ)
*「気滞」「瘀血」タイプの方へのアドバイスは連載第2回(2025年4月17日公開)に続きます。
*「陰虚」「水滞」タイプの方へのアドバイスは連載第3回(2025年4月18日公開)に続きます。
\好評発売中!/
『自律神経にいいこと大全100』
著:森田遼介