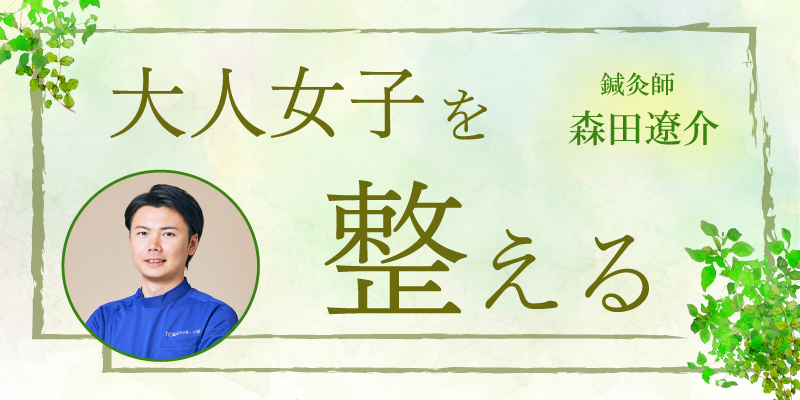
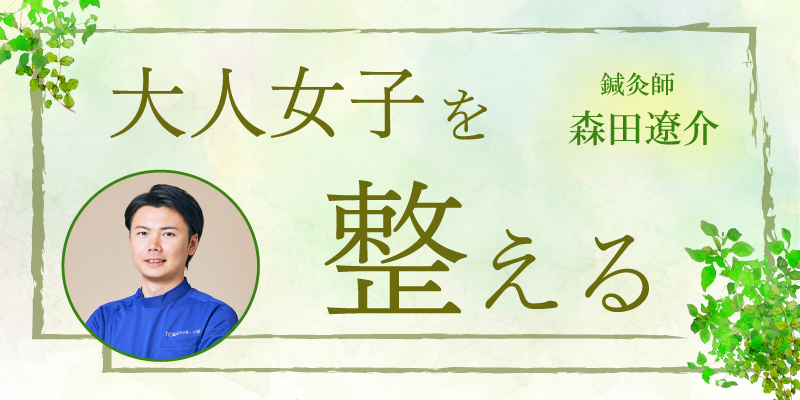

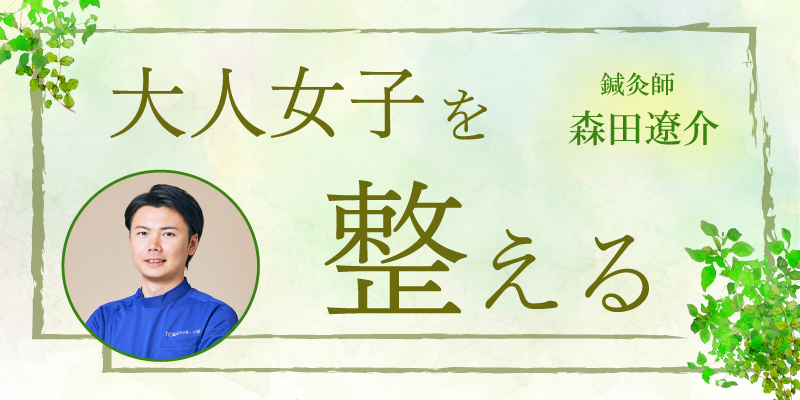
閲覧期限を終了しました。
TC鍼灸マッサージ院 院長
国家資格:はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師。鍼灸院などに勤めながら、勤務後や休日に個人で訪問治療を行う。予約1年待ちが続いたタイミングで2023年2月に独立し、4か月で予約満杯となる。現在は埼玉・東京エリアの訪問自費治療を中心に活動。
治療の特徴としては、全身の筋肉や内臓の調整をしつつ、不調の改善以降は再発の防止や他の大きな病気にかかるリスクを最小限にする、「未病」に対する治療で人生100年時代をできるだけQOL(生活の質)を落とさない目的の治療が需要として高い。
2021年2月NHK特番「東洋医学ホントのチカラ」・2021年4月NHK「あさイチ」・2024年4月フジテレビ「ホンマでっか!?TV」出演。
初の書籍『自律神経にいいこと大全100』(ワニブックス)のほか、『しんどい低気圧とのつきあいかた』(新潮社)ツボ監修。
X(旧Twitter) @harikyumorita
Instagram @harikyumorita
note @harikyumorita
COPYRIGHT(C) WANI BOOKS Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

ABJマークは、当サイトの電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号 第6091713号)です。ABJマークの詳細、ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら(https://aebs.or.jp/)をご覧ください。