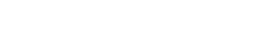二宮健監督の最新作『MATSUMOTO TRIBE』公開記念! 新鋭の映画監督4人による超スペシャル座談会! 【後編】
過去の作品と自分を比較し、逆算する

二宮:でも役者に限って言えば、そんなに教養がなくてもすごい人っていますよね。
松永:でもそれはね、俺はっきり思うんだけど、そういう選ばれた人って、本当に何万人に一人だから。
二宮:だとしても、いますよね。
菊地:それは役者に限らず、監督だっているよ。僕は助監督をやることに対してすごい悩んだんだけど、瀬々監督に誘われて助監督やることになった時、彼にこう言われた。「自主映画と助監督の二つで迷ってる? はっきり言えば、自主映画でどんどんやっていく才能ある奴って、お前の歳の時点でもう散々撮ってるよ。そういう奴らとお前が一緒だと思うな」と。それからは松永さんが言われたこととまったく同じで、「お前の個性なんてまずない。そんなものは忘れろ。だが、お前がこのまま続けて転がって行けば、何かには行き着くかもしれない」って。その時に僕は、ここで這い上がっていくしかないなと思った。それが僕の道筋。そして瀬々さんはこうも言ってくれた、「映画っていうのは良いことに、才能だけでいける奴もいるけど、努力だけでなんとかなる奴もいるんだよ」と。だから、悩んでる人は、もうその時点で才能ではいけないかもしれないと思った方がいいかもしれない。
松永:そう。そういう人は別次元なんだよね。だからこの記事なんか読んだとしても「ふーん」としか思わないだろうし。
二宮:そもそも読まないかも。
松永:そうだね。別のところに生きてるから。でもそういう選ばれた人っていうのは、本当に一握りでしかないから。ほとんどの人はそうじゃないからね。やっぱり努力の中で自分と向き合って、できないと思う中での反復でしかない。だからやっぱり過去を知って、勉強しなきゃいけないと思います。
二宮:知らないよりは知っていた方がいいですよね、絶対に。
松永:どこで自分を比較していくかって言ったら、そこでしかないよね。未来の自分は見れないわけだし。過去の傑作と呼ばれる作品や素晴らしい役者の方たちを観ることで自分と比較して、そこに行くためにはどうしたらいいかを考えないと。もしくは僕みたいに誰かに言ってもらうしかないんだけど、でも、ちゃんと導いてくれる師匠がいる人ってどれだけいるのか。僕は恵まれていて、自分が師匠だと思える人に出会えてめちゃくちゃ叩き潰されて、それは本当にラッキーだった。
二宮:マツ兄って、自分の言語を持つには過去の作品を摂取するわけじゃないですか。それをやった時期っていつですか? 要するに映画を観始めた時期っていつだったのかという質問なんですけど。
松永:本当の意味で映画を観始めたのは、二十三歳くらいかな。
二宮:そうなんだ。二十歳過ぎてそういうふうにシフトして上手くいく人ってすごい限られると思ってるんです。
松永:うん、だから俺本当に映画知らないと思う。もしかするとこのメンバーの中で一番観れてないかもしれない。遅いんだよね。監督をやろうと思って観始めて、三十五歳で『ピュ~ぴる』ってドキュメンタリーでデビューするまで約十年かかった。その何年か後に『トイレのピエタ』を撮るんだけど、やはりあの十年の間に観てたものがなんとなく影響として出ている。感覚的な話になっちゃったけど、そういうのは脳に埋め込まれてるんじゃないかと思う。あの十年がなかったら今の僕はない。
菊地:僕だったらレオス・カラックスの映画観て、あの映画の中のこういうカットやりたいとか、こういう芝居のあの瞬間を自分でも撮ってみたいという気持ちがあって、どこかで真似してる部分は無意識にある。そういう比較をして映画に取り組むと思ってるんですよね。だから好きな監督とか好きな映画、好きなカット、あの作品のこういうところを参考にしたいとか、映画監督をある程度続けてる人にはそういう部分を自然と持っていると思うんです。でも意外と、役者ってそれをしない人が多いんですよね。自分だけで勝負するというか。でも僕からすると、ちゃんと知識もあった上で初めて自分というものがあるんじゃないかという気がする。両方ないと駄目なんじゃないか。例えば「悲しい」という状況を役者として表現しなくちゃいけない時に、涙を流すなんてことは誰でも思いつくし簡単にできる。でもそれ以外のやり方で悲しいという感情を表現するには何があるんだろう、そういうリファレンスが圧倒的に足りない人が多いとは思うんですよね。良い役者っていうのは、監督や脚本家さんが考えたことをただやるだけではないですよね。そこに何かを上乗せすることができる。それができるようになるためには、別に映画だけじゃなくていいんだけど、いろんなことを見たり聞いたりしなくちゃいけないんじゃないかな。そういう意味では、話が戻るけど、松永さんがさっき言った「日常を豊かに生きてる人」っていうことですよ。
二宮:最近思うんですけど、役者たちの、割と品のない心理みたいなものが見えることがあるんですよ。文化じゃなくて、ある種の人間関係のグルーヴでなんとかしようとする。つまり、事務所があって、ツテがあって、こういう人間関係があってこういう知り合いがいて、そういうところに自分がいて、という基準で判断をする人が多いんじゃないかと。自分が実際にどういうパフォーマンスをできるのかということには意識が行ってない人が圧倒的に多いと感じるんです。
松永:確かに自分がフリーなのか事務所に入ってのるかをしきりとアピールする人っているよね。もちろん、良い事務所にマネジメントしてもらうことは続ける上で絶対必要だと思うんだけど、その前に、そもそも自分には個として魅力があるのかどうか、そこを問うことをしないのはダメだね。
二宮:それでまた辛いのが、こういう話をした時、そういう人たちって一応「うん、うん」って聞くんですよ。つまり自分のことだと思ってない。むしろ自分はできてると思ってる。だからやっぱり、誰かの言語で人は変えられないと思う。マツ兄はそういう素晴らしい師匠と出会って変わったって言うけど、でも良い出会いって自分で掴むものですよね。
松永:いや、俺は良い出会いだと思ってるけど、その演出家と出会ってる人は俺だけじゃないからさ。その演出家と出会ってどれだけの人が残ってるか考えたら、ほとんどいないかもしれない。結局さ、残るかどうかもその人に何かがあるかどうかだと思うんだよ。だってここに座ってる四人だってさ、いきなり集められた四人ではなくて、個々それぞれやってきた四人なわけでしょ。まだ未熟だけれど、でも何かの結果を残した四人。ここに来るまでもそれぞれ紆余曲折はあるわけでさ。その結果こうやって取材をしてもらっている、これは実はすごく有り難いことだよね。もちろんもっと上を目指すんだけど、ここに来るだけでもかなり振り分けられてるわけで。
小林:だから何を受け取れるかは、その人自身が積極的に受け取っていくしかないということですよね。
菊地:そう。どこで気付けるか。
松永:たとえばスポーツ選手だったらわかりやすい。短距離走を速く走れなかったら選手にはなれない、サッカー選手はちゃんとボール蹴れたりボールコントロールできなかったらプロにはなれない。一方で、役者や監督には明確な基準がない。これが本当に難しい。でも、僕が監督をやろうとした時に矢口史靖監督がこう言ってくれた。「松永君、すごいシンプルだから。自分が良いと思った作品を誰も良いと思ってくれなかったら、松永君は今この時代で映画を作れない人です」って。本当それだけのこと。作りたいものを作ってそれがこの瞬間にフィットするか、時代に合うかどうか。残酷だけどそうなんだよね。僕たちこの四人は、今の日本で作品を劇場公開してもらえて、名前を覚えてもらうことができる、そういう時代だったという。これがもし十年後だったら受け入れられてなかったかもしれないし。だからそういう意味では、努力した先に運も必要。役との出会い、作品との出会い、原作との出会い、脚本との出会い、そういう中で、いろんな項目にチェックが入っていった人たちしか残っていかないですよね。そのために何が正解でどうすればいいのか、それはわからないけど、必死にやるしかない。
菊地:我々も一緒ですけどね。しがみつくしかない。なんとかここまで踏ん張ってしがみついてるけど、心の中は恐怖しかない。今、自分は幸いなことに作品を続けて撮ることができているけど、十年後はわからない。その十年後がわからないことを楽しめる人間じゃないと駄目なんじゃないかなとも思うんですよね。明確なヴィジョンがあって、こういうふうにあがっていったら成功ですよね、というのがわからないのが面白い部分でもある。安定したいんだったらこんなことやっちゃ駄目だとも思うし。
松永:毎回就活だもんね。
菊地:毎回一本終わったら失業状態ですからね。仕事来なかったらそれまでだから。役者だって同じだと思うんですよね。僕の周りには、十五年くらいかけて小さい役ばかりコツコツやって、四十歳過ぎて良い役に当たってブレイクした役者もいます。
『MATSUMOTO TRIBE』という記念写真
――最後に、二宮監督、三人に聞いてみたいことはありますか?
二宮:今日話していてひとつ思ったのは、僕らももしかしたら「MATSUMOTO TRIBE」の一人かもしれないということです。だとしたら余計に、隙あれば遊び倒したいと思うんですよね。それに、僕と松永さんって結構歳が離れてるじゃないですか? そんな年上の大先輩の松永さんを撒き込んでるのってすごいエゴだと思うんです。でも同時に、自分が松永さんの歳になった時に同じように遊べてるんだろうかとも考える。だからこれは未来の自分への布石でもあるんですよね。自分はこうやって、先輩たちに真剣に付き合ってもらってたんだと。すごく図々しい遊びに付き合ってもらってたんだと。そういうものを、残せるうちに一個一個残していきたい。それで、三人に聞きたいことは、今の僕の意見を聞いた上での感想を聞きたいです。
菊地:僕は助監督を始めてからカウントするともう十五、六年映画の世界にいるんですけど、一個だけ絶対的な真理があると思っていて、それはやっぱり「面白いもん勝ち」ということなんですよね。もちろん僕らは命懸けで映画を作ってるけど、そもそもは、面白いことをやりたいという気持ちがあるわけですよ。それがこういう形になって映画になるのもひとつだし、たとえばみんなで本でも出してみるのも良いかもしれない。そうやって今後も面白がって楽しく、真剣に遊んでいけたら良いなと思いますね。
小林:この時期にこういうふうに映画を撮れたことは、ずばり、記念写真みたいなものではありますよね。そういうふうに残る作品があって良かった。『MATSUMOTO TRIBE』があることで、僕たち四人の関係値が外に見えたと思うんですけど、日本ではこういうことって珍しいじゃないですか。監督同士が一緒に何かやる機会ってそんなにない。あったとしても作風が近い人同士とか、出身学校が同じとか、雑誌の特集で並ぶ時くらいで。それがこういうふうに監督主導で記念写真を撮れたっていうのがこの作品のひとつの面白さだと思う。しかもその中心にいるのは、松永さん、菊地さん、僕の三人に何の関係もなかった松本ファイターだという。こういうものが残せたことは良かったですね。それから、この映画で考えさせられたことがたくさんあるし、これがきっかけで近くなった繋がりもある。出る前と出た後で自分にとってすごく変化があったので、食わず嫌いせずにやって良かったなと思いました。
――じゃあ最後、松永監督お願いします。
松永:みんなが言ったことと同じなんですけど、お客さんには、それが悲しい映画であれ苦しい映画であれ、観て良かったなと思ってもらいたいんですよね。それには何が必要かと考えると、まずは自分が作る時にワクワクしてるかどうかが大事だと思うんです。「こういう人を撮るのワクワクする」とか「ここで撮るのはワクワクする」とか「こんな題材で撮るのはワクワクする」とか、そういうワクワクを大事にしたい。そういう意味では、二宮がやってることには僕はすごく共感できる。この映画には、二宮じゃなきゃ甘えられないことがたくさんある。これを五十歳の監督がやったら、「もうちょっと違うやり方あるでしょ」と言われるかもしれない。二宮だからこそ周りを巻き込んでやれたんですよね。それだけに、この作品をちゃんと良い作品にしなくちゃいけないと思った。ワクワクだけで終わって沈んじゃ駄目だと思った。だから、お客さんがこれをどう観るのかは非常に興味深い。楽しみですね。……まとめると、僕はこの作品に参加して本当に良かったです。二宮に感謝したいですね。
二宮:(感極まり、松永監督に抱きついて)……マツ兄! !
一同:(笑)。
――二宮監督って甘え上手なんですね(笑)。
松永:それが技ですから。やっぱり監督には人たらしな部分がありますよ。プロデューサーに対しても、役者に対しても。この人の作品だからやろうって思えないと、たぶん続いていかない気がするな。「まあしょうがねえな」みたいな。
二宮:そうですよ!
一同:(笑)。

『MATSUMOTO TRIBE』
配給/Ashtray Arts
4月15日(土)より新宿武蔵野館にて1週間限定レイトショー公開
(c)2017 Ashtray Arts