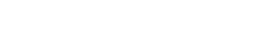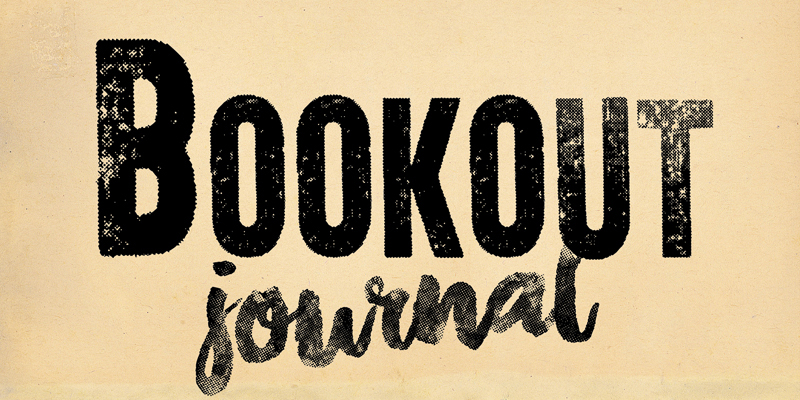
【後編】宝塚歌劇団 演出家 上田久美子さんインタビュー
BOOKOUTジャーナルとは
いちばん聞きたいことを聞く、
撮影/長谷川 梓
文/石井 美輪
———————————————————————————————————————————–
100年以上の長きに渡り、劇場を満員にし続ける宝塚歌劇団。
人を惹きつけてやまない舞台を作り上げる専属の演出家陣の中で、ここ数年でひときわ注目を集める女性がいます。
その女性とは、昨年大劇場デビューを果たしたばかりの演出家・上田久美子さん。
美しい舞台上で繰り広げられる、豊かで繊細な人間同士のドラマ。
3作続けて熱烈に支持される作品を世に送り出した上田さんとは、一体どのような人なのか?
ロングインタビューを前後編に分けてお届けします。
————————————————————————————————————————————

生徒も演出家も
舞台への敬意がなければ
一緒に作品は作れない
「宝塚歌劇団の公演を見たのは大学生の頃。劇場ではなくTVで観た『ベルサイユのばら』が初めての作品でした。どこかレトロで華やかな世界、男役が見栄を切ったときの興奮……カルチャーショックを受けるのと同時に、流行を追ったモダンなものがもてはやされる現代で、古式ゆかしい舞台が毎日劇場を満員にさせている、そこに興味を抱いたんです」
どこか客観的な視点で「ひとつの文化として素晴らしい」という思いで楽しんでいた、という。
「熱烈な宝塚ファンではなかった」それもまた上田さんの面白いところだ。
「本当の意味で愛情やリスペクトが芽生えたのは宝塚に入ってからなんです。先輩の演出家から言われた言葉に“生徒達が命がけで立っている、その舞台を裏方である私達が潰してはいけない”があるのですが。
その言葉通り、生徒達は稽古も舞台も真摯に敬意を持ってやっている。生徒達がよく口にする言葉に“お客様の明日の活力のために”がありますが、きれいごとのように聞こえるかもしれないけど、本当に皆それを信じて舞台に立っている。それまで深く知らなかったからこそ、皆が持つ舞台への思いや姿勢に触れるたび、敬意が大きく育っていったんです」。
自分の作品は氷山の一角。
“宝塚のために”
それが何よりも大切
稽古場のドアストッパーのブロックを枕に床で寝たことも。本番前になると過酷を極めた演出助手時代。
しかし「一度も辞めたいと思ったことはなかった」と上田さん。
「生きること、そして、仕事とは大変なものである。それは会社勤め時代に学んでいましたから(笑)。
また、物理的な大変さはあっても、精神面は逆に以前よりラクになったんです。
初日の幕が開けば、皆で作り上げた舞台がお客様に届く。
一次生産者から消費者へ、そのカタチが明確になったというか。歯車の一部になっていたときには見えなかったものが明確に見える。会社時代に抱えていた“私は何をしているんだろう?”そんな不安を感じなくなったのが大きいのかもしれませんね」
会社員経験がなかったらこの仕事の有難みを感じることなく辞めていたかもしれない、と微笑み
「先まで見通せる長い道を眺めるよりも、曲がり角があるサバイバル人生のほうが私には向いているのかもしれません。まあ、これは宝塚という組織に守られているからこそ、言える言葉なのかもしれませんが」
と笑った上田さん。とはいえ
「いつか自分の作品を舞台で。そんな強い気持ちも背中を押していたのでは?」とたずねると、返ってきたのは「それが全くなかったんですよ」という驚きの答え!!
「実は今も“自分の作品を舞台でやりたい”気持ちはそんなに強くなくて。ネタを思いついた時、これをあのキャストで出来たら…と夢を持つことはありますけど。こんなことを私が言うのもおこがましいのですが、私にとっては自分の作品より“宝塚歌劇団が続いていくこと”が大事なんです。そもそも、私が宝塚の門を叩いたのもその思いから。
例えば、日本が世界に誇る文楽などであっても、劇場は空席が目立ったり……そんな現実を目の当たりするなかでぼんやりと生まれた“面白い文化が続いていくために奉仕したい”という思いからなんです」
実は転職時「歌舞伎のプログラムを作る仕事や日本の舞台を海外に紹介する仕事だったり、宝塚以外の団体にも願書を出していた」そう。
「私の中に常にあるのは“宝塚を良いカタチで存続させるために貢献したい”という思い。
そのためには、本当は、演出家でなくてもいいのかもしれない。自分にそのセンスがあるなら衣装やセットのデザイナーになって貢献したいし、人を育てる才能があれば音楽学校で人材育成だってしたい。でも、私にはどちらの適性もなさそうなので、結局、台本を書くのがまだ一番いいのかもしれませんが(笑)」
日常を離れ別世界を楽しむ
それが宝塚の醍醐味だからこそ
誰もが楽しめる舞台にしたい
そして「どんな作品を描いていきたいか?」質問したときに続いたのが上田さんらしいこんな言葉。
「一人の演出家しかいないほとんどの劇団とは異なり、宝塚歌劇団には複数の演出家がいます。ゆえに、私は自分自身を大きい複合ビルの中の個人営業店だと考えているんです。
“うちはフレンチ”“うちはイタリアン”“うちは和食”おのおのの演出家がひとつの店であると。
美味しい店が集まれば、誰もが行きたいビルになる。私自身が寿司屋なら寿司の技能を磨きたい。
例えば悲劇なら悲劇、作風は一つでいいのかもしれません。
あれもこれも出来ますよと技能を披露する必要はないのかなと。
私は寿司職人だけどたまにはフレンチの腕も見せますよ、って寿司屋でフレンチを出されても、フレンチレストランにはかなわないでしょう?そのために、たくさんの演出家の異なった店があり、生徒という“素材”が、それぞれの店の一番得意な方法で美味しく料理される、それが宝塚なのかなと」
取材中、こんな印象的な言葉もあった。
「私が演出した舞台を人から“良かった”と言ってもらえるのは心から嬉しい。でも、私自身は自分の脚本演出が良いなんてまだまだ思えない。自分に才能があると思ったことも一度もないです。だからこそ、何度も推敲し“どうしたら面白い舞台になるか?”一生懸命考える」
「大変な現実から離れ、ひとときの間、別世界を楽しむ。それが宝塚の舞台の素晴らしさだと私は感じていて。
だからこそ“誰が見ても楽しめるものを”という気持ちも自分の中に強くあるんです。
そこで基準になるのが、前の職場で出会った人達。今はある意味、特殊な世界にいるので、自分の感覚というギアをニュートラルに入れておく意味でも、会社員時代に知り合った人たちとの繋がりは有り難いし、ずっと大切にしたい」
どんな高評価を受けようとも、舞い上がることなく冷静に「宝塚のために自分には何ができるのか?」客観的に俯瞰で考える。自分の主観で突っ走ることなく観客の目線で舞台を見ることができる。
その視点があるからこそ、上田さんの舞台は多くの人の心を動かすのだろう。
上田さんがどんな物語を宝塚の劇場に紡いでいくのか、これからも楽しみだ。

【PROFILE】
上田久美子(うえだ・くみこ)
宝塚歌劇団 演出家
2006年宝塚歌劇団入団。2013年『月雲の皇子―衣通姫伝説より―』、2014年『翼ある人びと―ブラームスとクララ・シューマン―』で高い評価を得る。2015年『星逢一夜』で宝塚大劇場デビュー。同作品で読売演劇大賞、優秀演出家賞を受賞。
宝塚歌劇 オフィシャルサイト
https://kageki.hankyu.co.jp/
上田久美子さん次回作品
『雪華抄(せっかしょう)』
作・演出/原田 諒
『金色(こんじき)の砂漠』
作・演出/上田 久美子