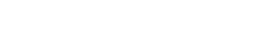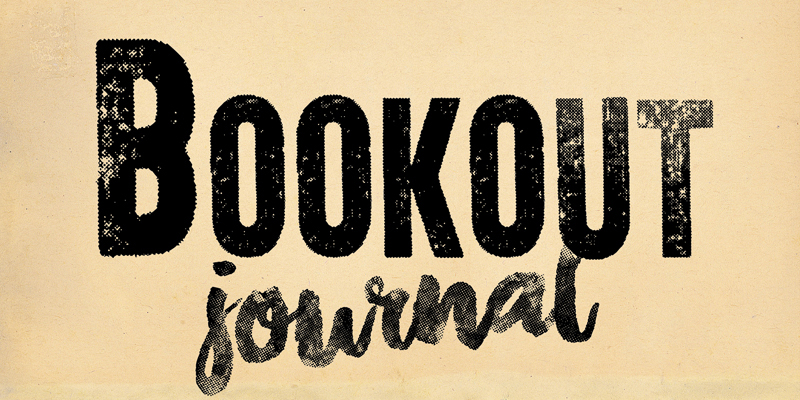
【前編】宝塚歌劇団 小柳奈穂子さんインタビュー
BOOKOUTジャーナルとは
いちばん聞きたいことを聞く、
文/石井 美輪
02年、宝塚歌劇団で演出家デビュー。以降、フランスの戯曲を下敷きにした『めぐり会いは再び』を始め、映画作品を舞台化した『Shall we ダンス?』、そして、あの人気アニメを題材にした『ルパン三世』と話題作を次々に手掛けてきた小柳奈穂子さん。その才能を育んだもの、そして、演出家を目指したきっかけまで、たっぷり語っていただきました。

文化的好奇心旺盛な大人達に
囲まれ育まれた知識と好奇心
「私は長野県の松本市で生まれ、3歳までそこで過ごしました。私が住んでいたのは“松本”と言っても栄えている中心部ではなく山奥の田舎町。民家もまばらで人もいない、一緒に遊べる同じ年頃の友達もいなくって。
遊びといえば、絵本を読んだり、子供向けのTV番組を見たり。リアルな人間よりもフィクションが身近な環境で育ったんですよ」
―なかでも夢中になったのが『くまくんのおともだち』『だるまちゃんとてんぐちゃん』『おふろでちゃぷちゃぷ』……両親が買い与えてくれた数々の絵本。「放っておくと、それぞれが好きな本を読み続けるような、読書好き一家の中で育った」という小柳さん。
「母親は大学の卒論がヘミングウェイだったとかで、家には古典文学の本がたくさんあったし。学生運動世代の父の本棚には、吉本隆明さんの本の脇に『ATG』(60年代から80年代にかけて芸術性の高いアヴァンギャルドな映画を製作していた映画会社)のビデオが並んでいた。
さらに、親族にも文化的好奇心旺盛な人が多くて。母方の祖父は戦時中の浜辺で“ヤシの木の繊維でカツラを作って『滝の白糸』を演じたんだ”と自慢気に話すような人でしたし、父方の祖父も浄瑠璃や歌舞伎が好きで、祖母も当時にしては珍しくいろんな国を旅していた。なかには『じゅげむ』や『目黒の秋刀魚』を覚えるとお小遣いをくれる落語好きの叔父もいたりして(笑)」
―文化的好奇心旺盛な大人たちに囲まれ「教えてもらわずとも、手を伸ばせばいろんなものがあった」恵まれた環境の中で知識を蓄え、好奇心をぐんぐん広げていった小柳さん。
「演劇との出会いを運んできたのも実はその親族だったんです。当時は毎年夏に松本で『現代映画フェスティバル』が開催されていたんですけど、その実行委員長をしていたのが叔父で。10歳くらいの頃、その叔父に誘われて観たテント芝居が私にとって初めての観劇体験だったんです。
テントを張って、その日の夜に上演して、翌日には跡形もなく消えてしまう……私の目にはそれ自体が非現実的というか、まるでフィクションのように映って。“いいな、私もあの中に入りたいな”と。“何かを表現したい”とかではなく“あの物語の一員になりたい”と思った。それが全ての始まりだったんですよ」