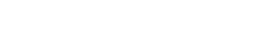【台湾茶のQ&A】ゆるく気軽に飲んでほしいという想いからお茶への疑問に答えてみました
優美でおいしい台湾茶。
淹れ方やお作法のハードルが高そうだけど、実は自由に楽しめるもの。好きなところをつまみながら自分の茶道を探す、台湾在住コーディネーター・青木由香さんのお茶ごとエッセイ。
私は日本でお茶のブランドを立ち上げた関係で、直接お客様にお茶を紹介する機会が増えました。
香香台湾(シャンシャンタイワン)というブランドなんですが、パッケージに描かれている台湾のおじさんや神様のキャラの関係なのか、私自身のキャラの問題か、試飲を勧めると台湾茶に詳しそうなオーラの人からはスルーされ、逆に飲んでいただけると「緑色だけど烏龍茶なんですか?」と言われたり、幅広い反応を浴びています。

烏龍茶といえば、ペットボトルの茶色のお茶とイメージする人も結構いて、烏龍茶すなわちお茶への興味と知識に差があると感じ、甘く香るこの烏龍茶が日本の日常にもっと入り込めないものか。
お茶の文を書いて、行商をするという行動でこの溝を埋めるべく、せっせと土嚢を積んでいますが、よく聞かれる質問に私なりにですが答えてみようと思います。

▲緑色の烏龍茶。日本では馴染みがない方もいますが、これも間違いなく烏龍茶。
烏龍茶って、お値段高め?
烏龍茶はグラム単位で見ると高く感じても、実は何煎も飲める。高級なものに手を出せばなんだって高いが、普通のものは言うほどコスパは悪くない。烏龍茶の茶葉は、日本茶や紅茶よりだいぶジャンボで、持久力が違います。

▲お湯をさす前の乾いた包種茶(左)とお湯をさした後の開いた茶葉(右)。
それに1~2煎で味がなくなるということがない。特別に良いお茶でなくても、お湯に浸しっぱなしにせず、1煎ごとにきちんと水切りをすれば、4煎は問題なし。しっかり丸められた球状のちょっと良い茶葉なら、7〜8煎目でもオッケーです。
あと烏龍茶は、種類によって花やフルーツ、蜜やミルクのような香りがある。よくコーヒーに使われる香りの例えと違い、初心者でも表現された言葉の通り感じられます。烏龍茶の香りでアロマ的な、そんな体験になります。
道具がないと飲めないもの?
道具にこだわらずとも十分美味しいんです。それが、台湾茶の底力。
茶葉を無駄にしない、という意味では道具も技術もあった方がいい。茶席をしつらえて雰囲気も楽しめたら、余計にお茶は美味しく感じますが、これらはお茶を120%楽しむための話。

もう一度言いますが、わざわざ道具は揃えなくても大丈夫。ただ、急須の容量に対して茶葉の適量は、少し意識した方がよくて、日本の家に転がっている急須だと台湾茶の急須よりはるかに大きく、茶葉はたくさん必要な上に、すぐに開き切ってしまい、とても残念。
烏龍茶は狭いところでじわじわ開かせた方が、1煎目、2煎目と毎煎ごとの味の変化を楽しめ、長く美味しく楽しめる。最近は良いお茶もティーバッグなっているからそれを選ぶのも手。もしくは、百均などでティーバッグの袋を買って詰める。もしくは、急須より遥かに安い蓋碗(蓋付きの湯呑み)を1つ用意する。こんな方法から始めるのもあり。
中国茶と台湾茶の違いは?
ざっくり言うと産地の違い。中国から台湾に来たお茶が、地形も気候も違うことで、茶の作り方も変わり発展したのが台湾茶。

たとえば、鉄観音は台湾産と中国産では全く違う味がするので、好みで台湾産か中国産かを選ぶ人がいる。中国産にはない、台湾特有の品種も増えています。
アッサムティーであっても台湾で品種改良された台湾バージョンがあり、それがまたインド人もびっくりの甘い香りだったりする。それら全てが台湾茶。台湾茶は、特に香りや甘みに注力して作られているので、その辺は、他地域のお茶にはないポテンシャルがあるのだ。
烏龍茶の色はどうして違うのか?
お茶の色の違いは、発酵度の違い。ぶっちゃけ、日本の緑茶もインドの紅茶も烏龍茶もみんな学名が同じチャノキ(茶の木)から作られていて、発酵の違いでそれぞれ違うお茶になっている。

▲発酵が軽い緑茶(左)、発酵が進んでいる紅茶に近い茶(右)。
発酵してないと緑茶、発酵してると紅茶。その間の半発酵のものが烏龍茶になるので、発酵が軽いと緑茶に近い緑色の烏龍茶。発酵が進んでいると紅茶に近い茶色の烏龍茶。その他(の烏龍茶)は緑と茶色の間の色となる。全く発酵してないのと十分に発酵したもの以外は全部ひっくるめて半発酵となるので、烏龍茶はバリエーションが多いんです。
前に飲んだ阿里山高山茶と同じものが買えるのか?
お茶の名は、「魚沼産コシヒカリ」的なブランド米みたいな地名使い(ex. 阿里山烏龍茶、凍頂烏龍茶など山の名前をつけた高山茶)とか、お茶の品種(ex.金萱茶とか紅玉茶)とかを使って、お茶を売る人が好きに名付けたもの。阿里山高山茶と名付けられた、同姓同名の別ものもたくさん存在してしまう。

▲ねじった縦長の文山包種茶(上)、小さな粒状に丸めた紅烏龍茶(左)、茶葉をそのまま乾燥させた老白茶(右)とさまざまな茶葉の形がある。
同じ産地でも作り手で味は変わるし、茶葉を摘んだ年が違うと気候も土の状態も変わるので、前に買ったものと全く同じとはならない。産地と製造者が一致しているものを求めると近いものが手に入る。お茶との出会いは一期一会と思って、大事にいただいて、新しい出会いを探すのも楽しみの一つ。
最後に私がとある茶人に言われた一言を
「茶葉選びもお茶の淹れ方も、飲んでみて好きと思えばそれがあなたの正解。お茶は嗜好品、自分の好きに楽しんでください。」
これは、お茶の美味しい淹れ方を聞いた私に「茶葉の量、温度、茶器を色々試して、自分の好きなお茶の味を探せばいいよ」と、とある茶屋の店主が言った言葉。この時、このおじさんは私の気に入ったお茶をどっちゃりプレゼントしてくれました。

突き詰めるとお茶によって、あーしろこーしろとかありますが、誰かが決めた淹れ方なんて中々覚えきれません。色々試して自分の好きなやり方で気に入る味を探して飲む。長々書きましたが、最後はこれに尽きるのではないでしょうか。
今日の一杯。<文山包種茶(ウェンシャンバオヂョンチャー)>

台湾産まれの品種で台湾を代表するお茶の1つ。文山(ウェンシャン)というのは、台北のお茶の産地・文山区という地名から。発酵のめちゃめちゃ軽い烏龍茶で、緑茶の爽やかさに花のような香りのお茶。緑茶の渋みも味わえるので、日本茶を華やかにしたようで日本人に親しみやすい。
茶葉は、ゆるく捻った細長い形。お湯は90℃くらいを目安からやってみると、自分なりの美味しい味を見つける近道かと。好きに試してみてください。発酵の軽い緑っぽい烏龍茶は、カフェインが多いので、眠れなくなる人は夜飲むのは控えめに。水出しもおすすめです!※
(※)おいしい水出しの淹れ方は1回目の「今日の一杯。」よりチェック!
*次回は11月11日(月)に公開予定です。
\青木さんのお店もチェック!/
『你好我好(ニーハオウォーハオ)』
https://www.nihaowohao.net/
日本から購入できるオンラインストアも!
https://nihaowohaostore.com/
\好評発売中!/
『暮らしの図鑑 台湾の日々』
著:青木由香
発行:翔泳社