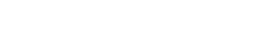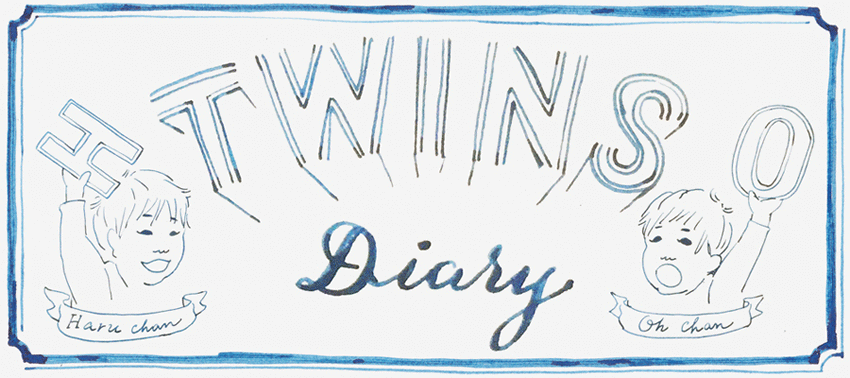
ふたごと三輪車
——————————————————————-
舞台や雑誌などエンタメ業に携わる
YURIさんが、双子の子育てを
あったかくもちょっとコミカルに綴ります。
子育て1年生さんにも役立つ実用もお伝えします。
——————————————————————-
こんにちわ。
ふたごがもうすぐ2歳になるという頃、公園で他の子の乗る三輪車や足でこぐタイプの乗用玩具をうらやましそうに見つめている2人を見て、「もっと大きくなったらね~」なんて言いつつ、そーいえば三輪車的なものっていつから乗れるようになるんだろう?と、ネットで検索してみると、ペダルなしの三輪車にいたっては大抵対象年齢が“1才半~”とあり、早いと1才からなんていうのもあることが発覚!
え。世の1歳代はもうすでに経験者なのか!
とくにうちの2人は車やバイクが大好きなのに!
公園に連れ出すだけで一苦労な我が家はウカウカしてました。そして、さっそく焦って買い与えることに。
でも、うちは同時に2台・・・。
色々飾りが付いていたり、かさばるものはNG。
重いものもNG。もちろん高価なものもNG。
そして行き着いたのはコチラ。

D-bikeミニ。
結論から言うと、コレほんとおススメです。
まず軽い。かさばらない。
デザインがオシャレで家の中でもジャマくさくない。
そして、前が2輪で、後ろが1輪という普通と逆パターンの構造によって、子どもがハンドルによりかかっても倒れにくく、足が後輪にぶつかりにくいとのこと。
なるほど!これすごく重要な気がします。
タイヤも柔らかくて、静かで床もキズつけません。
買った当初はまたがるくらいしかできませんでしたが、すぐに恐々前に進めるようになり、日に日に上達していき、1ヵ月もたたないうちに完璧マスター。
そして、購入から約9ヵ月、これに乗らない日はありません。余りに気に入っていて、外用にできず、家の中専用として使用していますが、狭い家の中をこれで縦横無尽に行ったり来たりしています。
パパさんが帰ってきてもこれに乗って玄関まで迎えに行き、お風呂時もこれに乗っていき、浴室の扉の前に「マッテテネー」と、駐車して浴室に入ります。
余りにD-bikeを気に入ってるので、外用の乗用玩具も買ってあげたいところですが、玄関に2台も置けない、保育園児なのでほぼ土日しか出番がない、などの理由から外用購入は見送り、とりあえず近所の無料で三輪車が借りれる交通公園に行き様子を見ることにしました。
その交通公園は、狭いながらも、信号機や踏み切りがあり、ぐるっと1周できる自転車コースの真ん中に、三輪車ゾーンがある形状なのですが、三輪車ゾーンなのに、舗装ガタガタ。しかも3台しかない三輪車はかなりの年代モノ。さすが区営。
今どきのシャレオツなD-bikeに乗り慣れた我が子たち。
果たして喜ぶのだろうか・・・と、一応、申込書を2名分記入し、これまたレトロなヘルメットを借りて三輪車ゾーンへ。
色目を変えて飛びつく2人。
自力では漕げないものの、一生懸命足で進んでいます。夢中。
2歳児にとって、オシャレ感などは無関係なことを再認識しました。
それ以来、「サンリンシャノリニイク~!」と、お気に入りスポットとなったのですが、三輪車は3台しかないわりにいつも空き空き。やっぱり諸々の悪条件のせいかしらと思っていたら、先日、めずらしく3台とも埋まっていました。
しょうがないので、ベンチで待機させようとすると、「あれ?ふたごちゃんですか?」と、声をかけられたので、「はい、そうなんですー」と答えると、「うちもなんですよ」と、そのママさんの足元には、2台の三輪車に乗る同じ顔2つ。
うちの子たちより1ヵ月年下のかわいらしい女の子2人をつれたそのママさんと、やんややんやと話していると、子供1人を連れて近くのベンチに座っていた男性が、我々に「ふたごなんですか?」と聞いてきたので、「そうなんですー、偶然~」と言いったら、「うちもなんですよ。もう1人は風邪で家にいますけど。」と。そちらもうちより1ヵ月下なだけとのこと。
なんということでしょう。
この広い世界の片隅、交通公園の三輪車ゾーンに、ほぼ同月齢のふたごが3組も同時集結。
もはやふたごゾーン。
テンションがあがり、色々話したいところでしたが、ふたご連れの親にゆっくり話す隙もなく、それぞれ転んだり騒いだりどっか行ったりするふたごに翻弄され、バタバタと笑顔で別れ、解散となりましたが、貴重な体験でした。
あ、今気づきましたが、やはりふたご家庭は、2台も買えるか!2台も置けるか!よし、交通公園!となるからでしょうか?
・・・集結理由判明。
愛車でお風呂場へ向かう図。

交通公園にて。
一番小さいヘルメットでもブカブカなので帽子の上にON。
キコキコキコキコ。と、懐かしい音もまたオツ。

(※注)昭和ではありません。

———————————————————————————————————-
Banner design&Illustration:CHALK BOY
http://chalkboy.me/