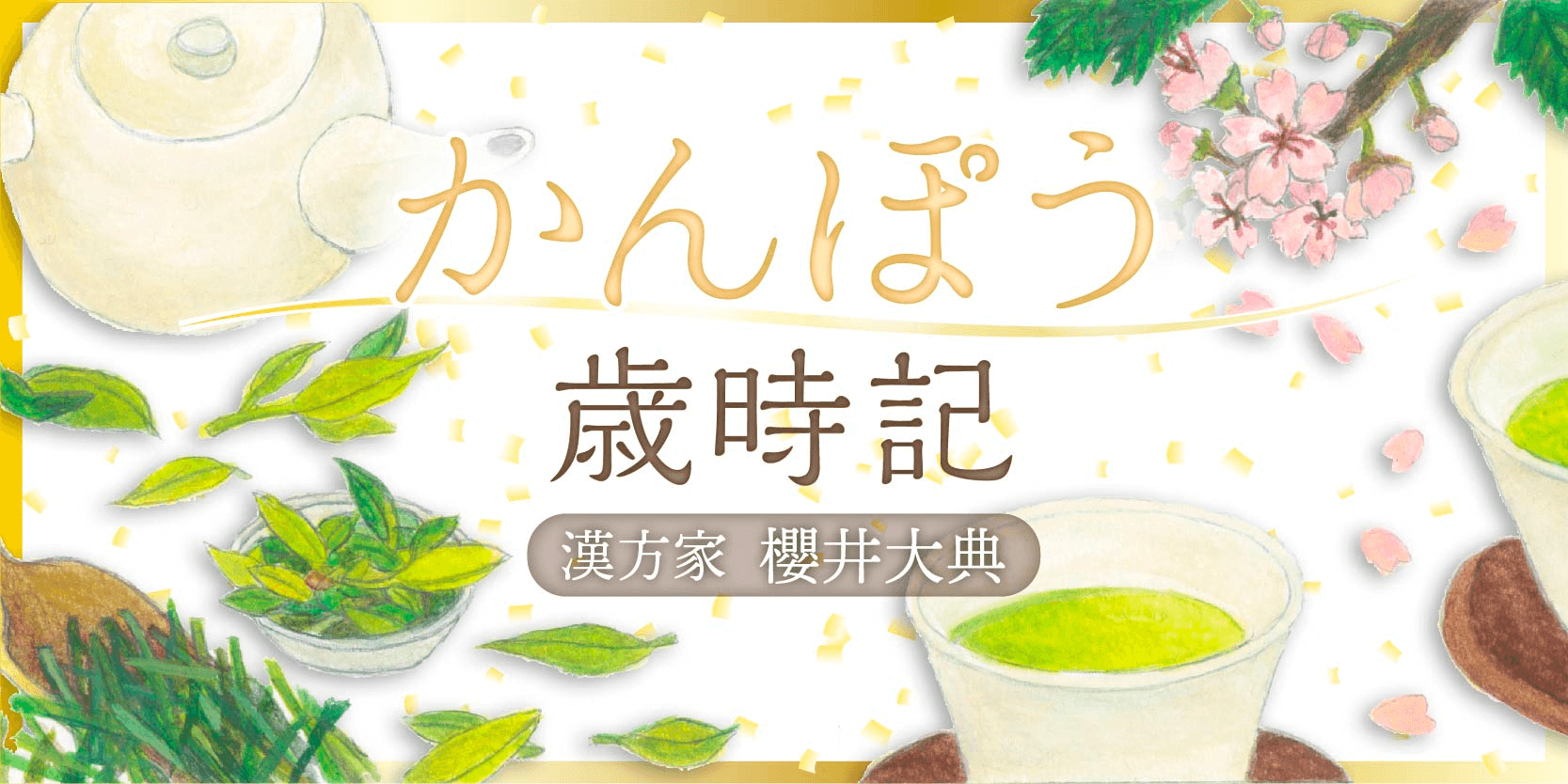
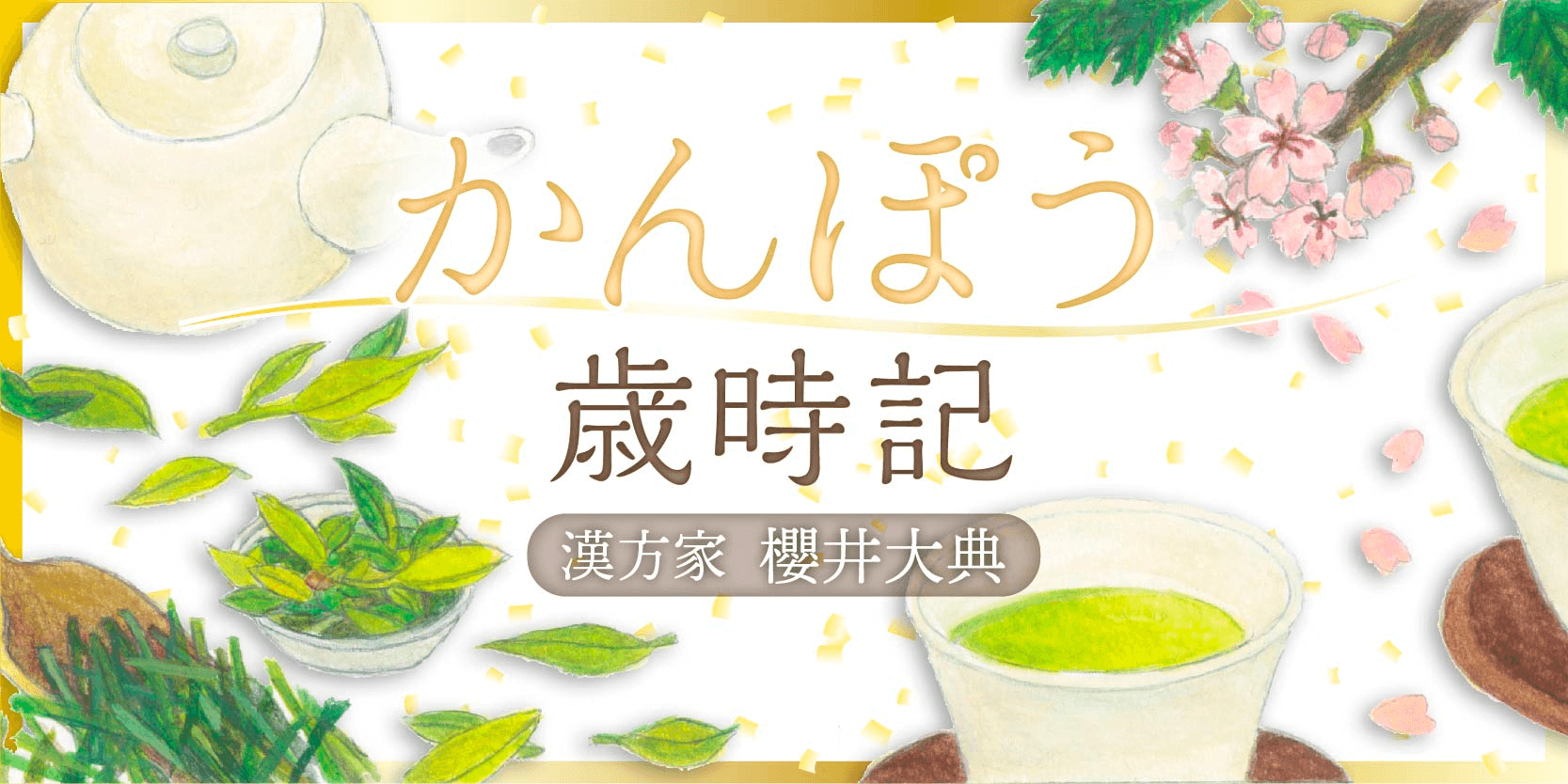

笠原将弘さんのYouTube、本当に料理の勉強になります。大根とホタテ缶のサラダ、リピートしています。今日もおつかれさまです。編集M
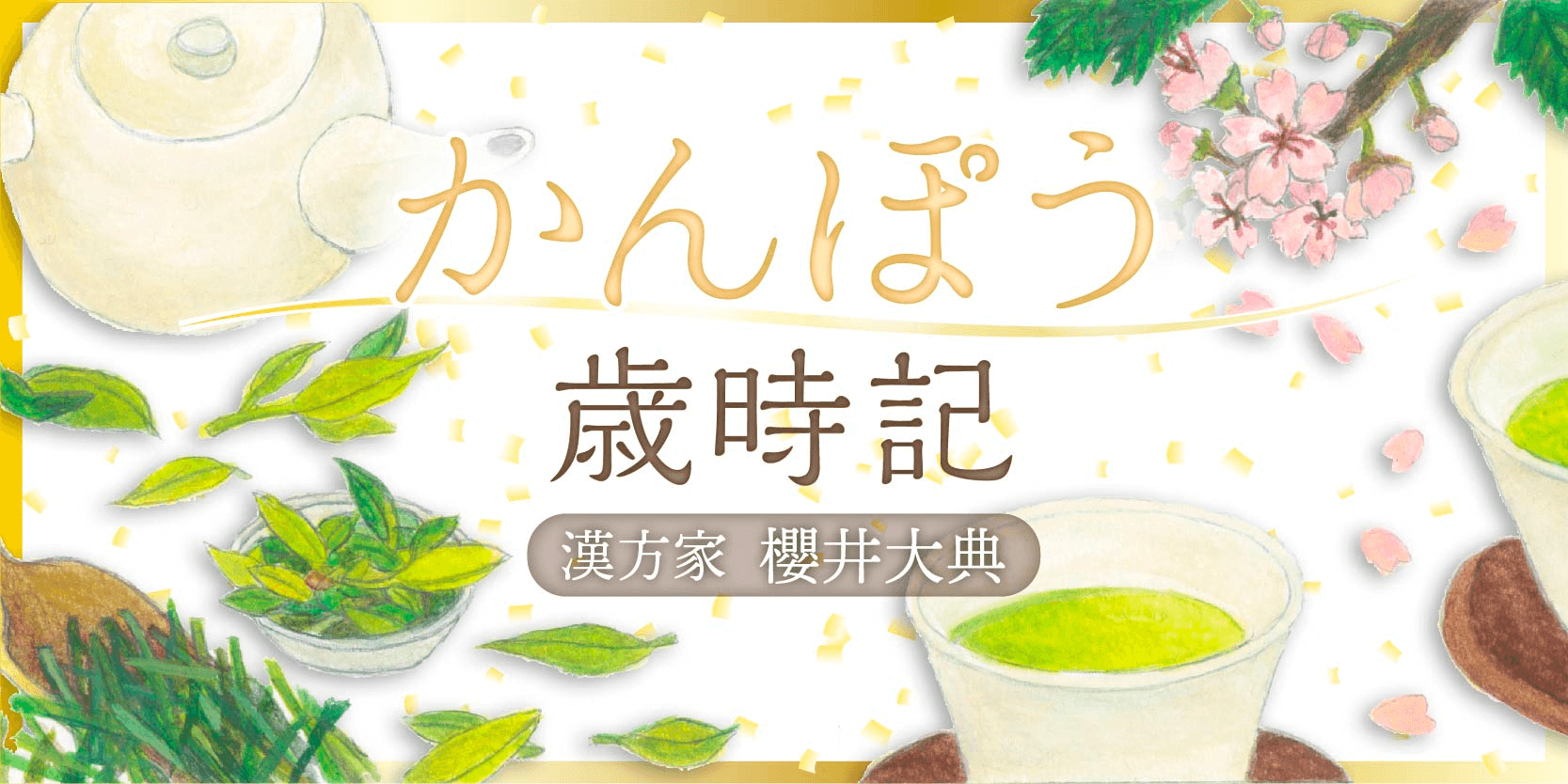
閲覧期限を終了しました。
アメリカ・カリフォルニア州立大学で心理学や代替医療を学び、帰国後、イスクラ中医薬研修塾で中医学を学ぶ。中国・首都医科大学附属北京中医医院や雲南省中医医院での研修を修了し、国際中医専門員A級資格取得。日本中医薬研究会に所属し、同志と共に定期的に漢方セミナーを開催。中医学の振興に努めている。
SNSにて日々発信される優しくわかりやすい養生情報は、これまでの漢方のイメージを払拭し、老若男女を問わず新たな漢方ユーザーを増やしている。
主な著書に『こころとからだに効く! 櫻井大典先生のゆるゆる漢方生活』、『こころの不調に効く! 気楽に、気うつ消し』(ともにワニブックス)、『まいにち漢方 体と心をいたわる365のコツ』(ナツメ社)、『つぶやき養生』(幻冬舎)、『漢方的おうち健診』(学研プラス)ほか多数。
X(旧Twitter): @PandaKanpo
Instagram: @pandakanpo
HP:https://yurukampo.jp/