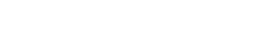それでも「女」の話がしたい
平成元年生まれのオタク女子で、会社員、フリーライター、同人ユニット「劇団雌猫」のメンバーと幅広く活躍するひらりささん。
浪費、コスメ、恋愛など女性にまつわる様々なテーマに向き合って来たひらりささんが、「女」について考える新連載がスタート。
連載開始にあたって、自身のこれまでを振り返りつつ、いま「女」について思うことをつづっていただきました。
自分が「女」であると最初に認識したのが、一体いつのことだったか、自分でも全く思い出せない。
初潮が来たときとか、ブラジャーを買ったときとか、痴漢されたときとか、告白されたときとか、初体験を終えたときとか。
「生殖にかかわる身体的な区別・変化を目にしたとき」「異性からの性欲・愛情の対象となったとき」に節目があったのだ、と振り返れたならば、それはとてもわかりやすいストーリーだろう。
もちろん、こうしたタイミングで自分が生物的に女性であるという認識が強化されてきた部分もある。けれど、本当にわたしを「女」たらしめてきたのは−−きっと誰もがそうだと思うけれど−−もっとぼんやりとした、細かくてささやかなことの連続だ。
たとえば、こんな瞬間を覚えている。

弟と違ってわたしだけが、クラシックバレエの教室に通わせられたとき。
小学校の学芸会で「動物園の園長」役に一人手をあげていたのに、「園長の威厳が出せない」と言われて、立候補していなかった他の男子がその座を得たとき。
「おじいちゃんから大学に行かなくていいと言われて悔しかったから、りさにはそういう思いをさせたくない」と母親に言われ、中学受験塾に通うことになったとき。
私服OKの中高一貫女子校に通い始めたけれど、市販の制服風コスチュームを着てミニスカ白ソックススタイルで登校するのが、“女子高生”らしくて “イケている”という空気があったとき。
クラス合宿でなんだかんだ女子学生ばかりが飲み会の片付けをしているとき。
将来一緒に住もうねと言い合ってペアリングをつけていた同性の同級生に、彼氏ができたとき。
地元で飲んだ後「この時間に夜道を一人で帰るなんて、絶対に危ないからやめてほしい」と、男性から強く言われたとき。
相手も私も無意識だったものもあるし、相手が良かれと思ってとった言動もあるし、性別とは別の要素が絡んでいるかもしれないものもある。こうした過程で、自分が「女」であることに疑いを持ったり抗おうとしたりしたこともあった。思春期にボーイズラブを濫読するようになったのも、少なくともわたしの場合は、自分が「女」になっていくことへの一種のカウンターだったと解釈している。

それでも現在わたしは「女」をやっていて、多分これからもやっていくようで。ここが嫌だあれが理不尽だと思うことは山ほどあり、それは絶対に変えていきたいのだけれど、そういうところも含めて、「女」というアイデンティティとべったりくっつきながら、毎日を生きている。「女」というラベリングによって、どこか「私」の個別性がかき消されてしまいそうな焦燥をいつでも感じていたはずなのに、できあがった30歳の自分を見てみると、「女」というラベルを剥がしたり戻したりした跡が、わたし個人にとっても大きな役割を果たしている。
女であるゆえに巻き込まれた、そんな経験はしなくてもよかったなと思う出来事は心底あるけれど、今「女」であるわたしのことは、嫌いではない。だからこそ「女」についてもっと知りたいと思っているし、わたしとは違う様々なやり方でこのラベルと戦ってきただろう周囲の人々への関心がある。「女」を難なく着こなしているように見える人から、自分以上に「女」と折り合いがついていないように見える人まで、話が聞きたい。「女ってこういうもの」「女ならわかるよね」と雑にくくってくる人々に抗いたい。