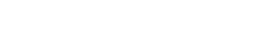わたしが女子校を礼賛したくない理由 #それでも女をやっていく

わたしのつまずきは、中学一年生の時点で起きた。球技が苦手なくせにうっかり運動部に入ってしまったところ、「足を引っ張る部員」として、仲間外れが発生したのだ。「練習についてこれてない」とか「ルールを守れない」とか、大義を持つ集団から弾かれる雰囲気は、小学校で経験した一過性のいじめよりもよほど心にきて、たぶん現在の人格のひねくれたところにも影響していると思う。運動部生活の中で最もよく聞いた言葉は、「前代未聞」だ。我ながらよく覚えているなと笑えるのが、ある月の部費を、母親から渡された銀行ロゴの入った封筒で持って行ったら、「無地の茶封筒じゃないと受け取れない」と同級生の女に突き返されたことだ。校則は4つしかないが、なんだかよくわからない生徒間の決まりごとがじゃんじゃか作られており、それは部活という組織体を通じて、上から下へと受け継がれていた。今でも銀行ATMで封筒を見ると、当時のことが浮かんでしまう。運動能力だけでなく、「可愛い」「イケてる」がシビアに評価されていて、その判定をクリアした子が、先輩からも同級生からも優しくされていた。
それでも6年間、家庭のゴタゴタがありつつも、ドロップすることもなく通いきったのは、学校の中で「居場所」を見つけることもできたからだ。部活で疎外されるスケープゴートは相当数いたが、別の部に転入したり、他のコミュニティを見つけたりした人間が、執拗に攻撃されることまではなかった。わたしも、中学2年になると同時に退部届けを出し、文化系のまったりした部活に移ってからは、かなり穏やかに過ごすことができた。
友達も増えた。コミックマーケットに誘われて一緒にイラスト本を買ったり、当時人気になり始めていた西尾維新の話で盛り上がったり、それぞれ自分のイラストを上げるホームページを作って“相互リンク”になり、キリ番を踏んで記念イラストを贈り合ったり……。わたしの自意識がこんなにも「オタク」としてのアイデンティティと結びついているのは、そのコミュニティがシェルターとして機能していたからだろう。女子校の同性同士ですら、「女」として価値があるかどうかの品定めは存在していたが、オタクグループに所属して初めて、「可愛い」「イケてる」の呪縛から解放されたのだ。
そして、「可愛い」「イケてる」子たちが常に強者というわけでもなかった。他人が羨むものを持っているとされる人間にだけ向けられる陰湿さもあった。当時から存在していた中高生向け掲示板サイト「ミルクカフェ」をのぞけば、あの子は遊んでるだとか、可愛いけど性格が悪いとか、彼氏とどうだとか、そういう根も葉もない噂が山ほど書き込まれていた。

誰もかれもが刃を向け合って、互いの心身を削りあいながらも、致命傷はかろうじて免れていた。それは大半の人が自分なりのシェルターを見つけたからもあったし、外側の世界の力学に立ち向かう日が近づくにつれ、この世でたった230人の、同じ学舎で過ごす人間同士の不協和に固執することは、時間の無駄でしかないことを認識し始めたからだろう。塾に通い始めることでそれに気づく子もいれば、インターネットで人間関係を作ることでそれに気づく子もいた。来るべきときが見えてくると、互いに傷つけ合う暇はなかった。もう少し優しい見方をすれば、クラス替えという強制的なシャッフルで出会いと別れを繰り返すうちに、お互いの良いところも悪いところ、気の合う人間合わない人間の傾向というのをそれぞれが学習し、不用意に摩擦を起こさない技術が身についたというのもあったかもしれない。とはいえ、「人の話を聞く」がCのわたしは、同級生と比べてもかなり遅くまで、あれこれ失敗と後悔を繰り返したのだが……。
嫌な思い出を出力してみたつもりだが、やっぱりわたしは「女」が好きだから、どこかで自分たちへの自己愛が隠せていないだろう。この文章もむしろ「それはそれで美しい思い出と言えるのではないか」ととられてしまいそうで、書いたくせに、厭だ。せめて、併せて記したいのは、同級生同士では次第に矛をおさめ、善き隣人であろうと努力するようになったわたしたちも、男性教師にはかなり辛辣だったなということだ。たとえば、「前の授業が体育だったときに、わざとゆっくり着替えて、男性教師が教室に入れないようにして笑う」とか、「『あの先生、男なのに○○してキモいよね』のような陰口を言う」とか。もちろん女性教師へのおちょくりや陰口もあったが、生徒たちが相手を「軽んじていい」と思っているとき、その性別は確かに念頭にあった。
総体としての男性への恐れや、個別の性嫌悪を引き起こす体験を持っていたからこそ、目の前の人間に対してそうした態度を取ってしまっていたのはあるだろう。しかし彼らをある種の仮想敵を仕立てることで自分たちの結束を確認していた側面も、確実にあった。あれは「女」の狡さではなくて、「集団」の無邪気な残酷さだった。その残酷さに身に覚えがあったからこそ、男性だらけの大学で浴びた「女子」扱いの洗礼に一層ショックを受けたのかもしれないと、今は思う。