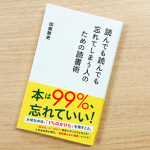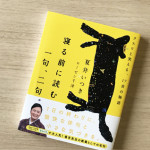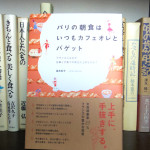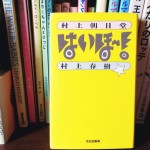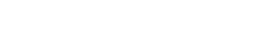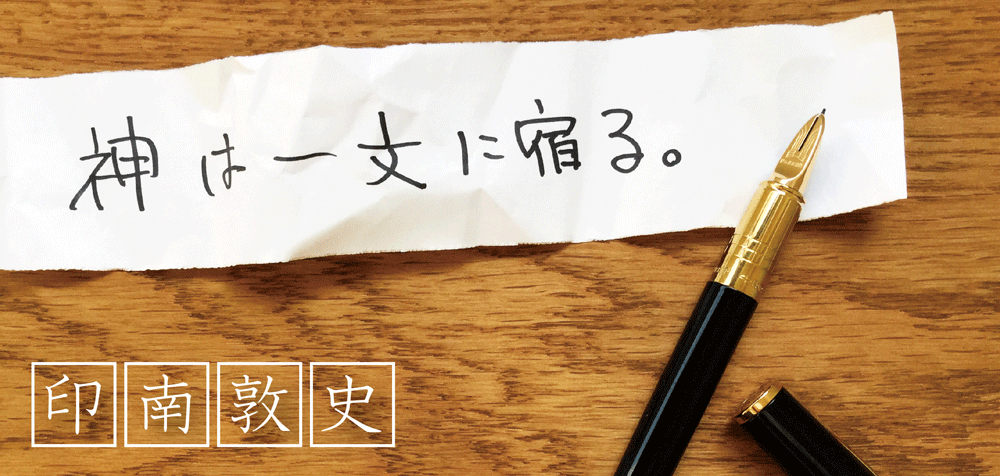
カテゴリー
-
- Categories
- BOOKOUTジャーナル
- Podcast
- ウェブ版+act.
- エンタメ
- ライフスタイル
- レシピ
- 占いのバトン
- 旅
- 美容・ファッション
- 著者インタビュー
- 趣味・楽しみごと
- 連載コラム
- 健康・ダイエット
- 特集
- 過去の連載
- arikoの生活
- それでも「女」をやっていく
- ゆとりフリーターの「ぬるい哲学」 みんな違って、みんな草
- 占いを取り入れて暮らしています。
- 多分、なんとかなる イタリアその日ぐらし
- [ミニレビュー]書店員さんおすすめ本
- 12か月の暮らしごと 杉浦さやか
- LAに暮らすEMIKO STYLE
- Twins diary ~YURIの子育て日記~
- イラストレーター まるちゃんのパン便り
- ウサギさんと学ぶ○○のお作法 STUDY
- おくすり飯 大友育美
- おしえて!真核生物くん
- かんぽう歳時記
- しろくまななみんの #ガラスペンとインク沼
- たのしい4コマ劇場
- どっちが正しい? 幸せになる猫暮らし
- ひろぽと歩けば
- ファッションディレクター ウツノアイのFashiongram
- ヘアメイクアップアーティストyumiのPlus1メイク
- ぼくは死ぬ前に、やりたいことをする!
- ホテルで暮らしの模様替え 本多さおり
- マイフィンランドルーティン100 in フィンランド
- みどりのくすりばこ 森田敦子
- 今夜もマッカラン 三尋木奈保
- 今日の旬、いただきます。 井上裕美子
- 僕のテレ東道 濱谷晃一
- 好きな人と好きなだけ一緒にいられる「恋愛心理学」 村松奈美
- 寺澤ゆりえのおしゃれ Sketch
- 恋愛迷子に贈る しあわせのコンパス
- 日本〇〇ブス図鑑
- 星の裏時間 橘寧乃
- 普通の恋ができない 山田玲司
- 杉浦さやかのつくる、つつむ、おくる。
- 現代寓話集 森達也
- 神は一文に宿る。 印南敦史
- 神様と顧問契約を結ぶ方法 -ソウルセッション- yuji
- 神田恵実の超忙でもヘルシーごはん
- 私たちの現在地~広くて深いここだけの話~
- 編集長のおしゃれごと
- 自分を好きになる 数秘術キャラ占い
- Categories