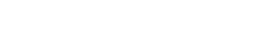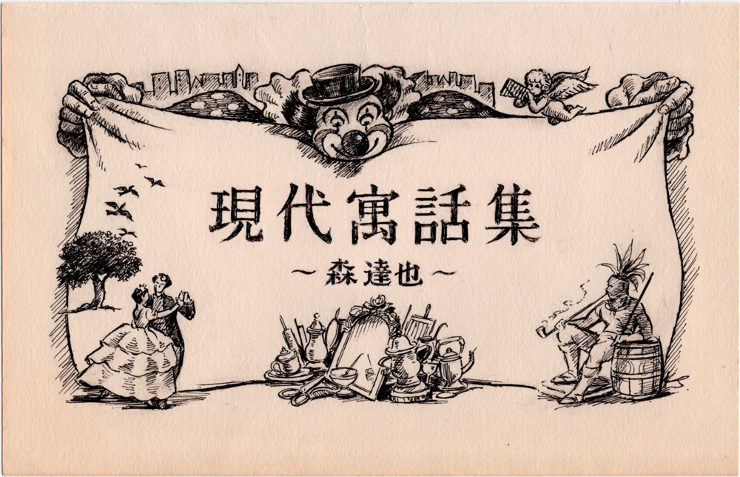
第1話 鬼ヶ島再襲撃
キジのこの主張に対して、文章はともかく映像は紛れもない事実でないのか、と反論する人がたまにいる。残念でした。確かにフレーム内は事実だが、そのフレームを選んでいるのはカメラマンでありディレクターだ。もしもアングルや撮影ポジションを変えれば、まったく違う光景が現れる。さらに映像の場合は、撮影後に編集という過程がある。カットのつなぎかたによって意味が変わる。つまりモンタージュ理論だ。そしてこの意味を選択しているのも、結局のところディレクターである自分なのだ。
テレビ・ディレクターとして仕事を続けながら、キジはこのジレンマに悩み始めた。客観的な真実など撮れない。あったとしても虚と実は分けられない。提示できるのは自分の視点なのだ。主観と言い換えてもいい。それは虚でもあるし実でもある。それ以上でも以下でもない。
ジャーナリズムを志す者にとって、真実という言葉は麻薬のように魅力がある。キジにもそんな時期があった。でもオウム真理教が地下鉄サリン事件を起こしたとき、現役信者たちのドキュメンタリーを一人で撮ったことで、自分が伝えられることは結局のところ自らの主観なのだと気がついた。
悩みながらキジは決意した。客観を装わないこと。主観であることを隠さないこと。現場で感知した自分の思いを裏切らないこと。所属する会社の上司や視聴率や世相に過剰に迎合しないこと。
ただしキジのこのスタンスは、組織人としては失格だった。使いづらいディレクターとの評判は広がり、少しずつ仕事は減り、会社に居場所がなくなって辞表を出し、今ではその日暮らしのありさまだ。家に帰れば腹をすかした家族が待っている。雛は毎年春先に数羽生まれる。教育費だけでも大変だ。次の仕事はTBSの報道番組だが、ロケの予定は来月だ。少し間が空いている。鬼ヶ島のこの仕事は、スケジュール的にはちょうどよい。
保守速報の見出しをじっと見つめながら船頭は、「こらぶったまげた」とつぶやいた。
「鬼の奴ら、こんなことを内心は企んでいたんか」
「あきれますよね」
「ミサイル基地など冗談じゃなかっぺよ」
「放っておいたら攻撃されます」
「敵基地攻撃論だな。要するに先手必勝だっぺ」
「…専門用語をご存知ですね」
「自民党の議員が言ってたっぺよ。これは自衛だんべ。子や孫を守らんといけん。こらあ許せん。お仕置きせねばダメだ」
うなずきながら桃太郎は、サルにもう撮影はいいよと目で合図を送った。オンエアで使うのは後半だけだ。ならば鬼の脅威に脅える村人たち、という構図を強調できる。
うなずいてカメラをしまうサルを横目で見ながら、キジは「ディレクターは私です」とふいに言った。三人が同時に自分を見た。でも言うべきことは言わねば。
「アドバイスは歓迎します。でも撮影や編集については、私が判断します」
「何だよ急に」
そう言いながら桃太郎は下卑たように笑う。文字にすればニヤニヤ。でもこれも、結局はキジの視点なのだ。もしも桃太郎に好意を持っている人ならば、この笑みをニコニコと記述するだろう。それが表現の本質だ。わかったわかった。恭一も偉くなったよな。今回のおれはレポーターだ。現場での指示や編集はおまえに任せるよ。
三人は鬼ヶ島に上陸した。あとは前回の通り。海岸で遊ぶ鬼の子供たちをまずは追いかけ、次に子供たちを救おうと向かってくる鬼の母親と父親を撮った。前回のとの違いは、スマホを手にした桃太郎は自分の突進シーンを撮らせると、あとは日陰に寝転んでSNSで実況中継をしていたことくらいだろう。どうやら今回も桃太郎が手引きしていたらしく、沿岸警備隊や他のメディアが島に上陸してきて、鬼たちを追いかけ回している。その光景をしばらく見つめてから、キジはサルの和幸に「カメラの向きを変えるぞ」と耳打ちした。
「向きを変える?」
しばらく考えてから、和幸は大きくうなずいた。鬼たちの傍に近づくと、泣きべそをかいている子供の肩をそっとさすってから、不安そうに自分たちを見つめる鬼たちに小さくうなずいて、和幸はカメラを肩に担ぐ。ただし向きは180度逆だ。鬼たちから見たメディア。鬼たちから見た捜査権力。鬼たちから見た社会。フレームの中には、スマホに夢中の桃太郎も映っている。
編集を終えた報道特集はTBS系列で放送された。オンエア中に桃太郎から何度も電話が来たが、キジは黙殺した。VTRが終了して、スタジオにいた金平茂紀キャスターは、「これはフェイクではありません。でもトゥルースでもありません。事実の断面のひとつです」とコメントした。とっぴんぱらりのぷう。
(イラスト 鈴木勝久)