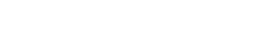第2話 石のスープ
「じゃあ今夜も野宿か」
「雨が降りそうだ。それは避けたい」
「何も食べなければ死んでしまう」
しばらく顔を見合わせてから、三人は門をくぐって村の敷地に入る。細い道をしばらく歩くと、前方に小さな灯りが見えた。小さな農家だ。暮らし向きは豊かではないようだ。三人はそう考えた。一番目の兵隊が木の扉をノックした。でも反応はない。留守かな。二番目の兵隊が小声で言う。でも灯りがついているよ。三番目の兵隊がやっぱり小声で答えた。
「誰だ」
ふいに男の声。一番目の兵隊はちらりと扉の上に視線を送る。小さな監視カメラが設置されていた。ならば軍服で誰かはわかっているはずだろう。そう思いながら兵隊は、「夜分にすみません。私たちは元兵隊です」と扉の隙間に顔を近づけて言う。
「実は、非常にお恥ずかしいのですが、事情あって持ち金が尽きてしまい、二日間食事をとっていないのです。大変申し訳ないのですが、パンを一切れでも頂けないかと思ってお訪ねしました」
扉が少しだけ開き、髭面で目の大きい男が顔を出した。この家の主なのだろう。三人の兵隊は思わず後ずさった。男の全身からは、知らない人への敵意が発散されていたからだ。
「パンを恵め、だって?」
男は言った。声には明らかに棘がある。これは一筋縄ではゆかないようだと思いながら、一番目の兵隊は、「朝から何も食べていないのです」と哀れな声で言った。
「知ったこっちゃねえ」
男は言った。
「おまえさんがた、看板は見なかったのか」
「特別警戒実施中の看板ですか」
「村の入り口にあったはずだ」
「気づきませんでした」
そう言って三人はとぼけた。「もうずいぶん暗くなっていたので」
「とにかくこの村は、よそ者はいっさい断りだ。うちだけじゃない。どこの家に行っても同じだ。治安が悪くなる。とっとと村から出て行ってくれ」
取り付く島がないとはまさにこのことだ。でもここで引き下がったら、今日も一日、昨日に続いて何も食べずに過ごすことになる。しかも野宿だ。兵隊たちは必死に言った。
「お願いです」
「一片のパンが無理なら一口のスープだけでもよいのです」
「このままじゃ死んでしまいます」
「知ったこっちゃねえ」
言うと同時に男は兵隊たちの目の前で扉を閉めた。内側から鍵をかける音がする。三人の兵隊はしばらくその場に立ち尽くした。この村には戦争が起きる前、何度か来たことがある。当時の村人たちは優しかった。でもここ数年、その村人たちの様子が変わってしまった。
その最大の要因はメディアだ。特に戦争が起きる前と始まってからしばらくのあいだ、メディアがひっきりなしに、敵の国の兵士たちの残虐性と危険性をアナウンスし続けた。理由の半分は現政権の指示でもあるけれど、残りの半分は、そうした報道にスライドしたほうが視聴率や部数を上げることに貢献するからだ。
こうしてテレビを見ながら、不安や恐怖は増大し、他者へのセキュリティ意識が高揚した。監視カメラの増殖と併せてセキュリティ関連会社の業績は急激に上昇し、安心や安全を訴えるテレビCMを頻繁に目にするようになったのはこのころからだ。小学校の校門はオートロックが当たり前になって、危機管理やリスクヘッジなどの言葉は流行語になり、危機管理学部を新設する大学も急増した。
この時期に、日本中の村でゴミ箱が透明になった。もしも爆発物など危険なものを入れられてもすぐわかるように、との理由だと思うが、爆発物を剥きだしのまま持ち歩いてゴミ箱に入れるテロリストはまずいないだろうし、そもそもそんな事件はそれまでに一度も起きていない。でもあっというまに国中の村でゴミ箱が透明になった。
変化は他にもある。公園や駅のベンチだ。仕切りが入ることが当たり前になった。それまであったベンチを撤去して、なぜ仕切りを入れたベンチをわざわざ設置するのか、最初はわからなかった。でもここ数日、歩き疲れて公園のベンチで仮眠をとりたいと考えたとき、三人は仕切りの意味に気がついた。横になれないのだ。
ベンチで横になるような人は普通の生活をしていない人。流れ者かもしれないしホームレスかもしれない。いずれにしても社会の異物だ。そういう人を排除しているのだろうか。そういえばほぼ同じ時期に、在日外国人を排除せよなどとヘイトスピーチを往来で繰り広げる男や女たちのデモが行われるようになった。セキュリティへの希求は社会の同質化を目指す。不安と恐怖におびえながら人々は、同じ属性を持つ人たちでまとまりたくなる。自分たちとは違う集団に帰属する人たちと自分たちとを分離したくなる。
こうして社会の集団化と分断化は並行して起きる。