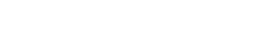第2話 石のスープ
家の前でしばらく考え込んでから、三人はとぼとぼと歩き出した。二番目の兵隊が足もとにあった握りこぶしほどの大きさの石を拾った。しばらくそれを見つめてから、二番目の兵隊はその石を持っていた垢じみたタオルで包んで懐に入れ、二人の兵隊に耳打ちしてから、再び家の前に戻って扉をたたいた。
「何なんだ」
男の声。相当にいらいらしているようだ。
「警察に連絡するぞ」
「パンもスープもあきらめました。でもせめて、空のお鍋とスプーンだけでよいのですが貸してくれませんか。小川の水を入れて石のスープを作ります」
「石のスープだって?」
しばらく間が空いてから、扉が少しだけ開いた。
「何だそれは」
「言葉どおりです」
そう言ってから兵隊は、布でくるんだ石を懐からとりだした。
「この石と水を鍋に入れて火にかけます。するとスープが出来上がります」
「俺をかつごうってのか」
「とんでもない。この石は我が家に伝わる家宝です」
しばらく考えてから、男は兵隊に水の入った鍋とスプーンを貸した。礼を言って三人の兵隊は、落ちていた枝などを拾い集めてから簡単なかまどを作り、鍋に石を入れて火にかけた。
ぐつぐつとお湯が沸騰し始めたころ、我慢できなくなったのか、男はのっそりと家の中から現れた。見上げるほどの大男だ。しかも手には木刀を持っている。
「本当に石でスープができるのか」
「もう少しです」
男に続いて、その妻や子供たちも戸口から出てきた。近所の家からフランソワーズやマリーも顔を出す。その後ろから夫や子供たちも現れた。
「できるわけないわよ」「だってもう作り始めているよ」「どんな味なのかしら」「石の味だぜ。美味しいわけがない」「そもそも石に味があるのかしら」
人はどんどん増えてきた。やがてお湯が沸騰する。二番目の兵隊は石のスープを一口すくって口に入れてから、眉間に皺を寄せて、うーんと唸った。一番目と三番目の兵隊も一口ずつ口に含んでから、やっぱりうーむと唸る。
「…どうだ。できたのか。どんな味だ」
木刀を持った大男が、鍋の中を覗き込みながら言った。
「どんなスープにも、しおとこしょうはかかせませんな」と、ヘいたいたちはなべをかきまぜながらいいました。
するとこどもたちが、しおとこしょうをとりに、はしっていえにかえりました。
「こんなにいい石なら、これだけでもうまいスープになるだろうが、もしここににんじんがはいれば、もっとおいしくなるんだがなあ」と、へいたいたちはいいました。
「あら、にんじんのいっぽんやにほんならあったとおもうわよ」フランソワーズはそういうと、いえまではしっていきました。
そしてあかいかけぶとんのしたからにんじんをたくさんとりだして、エプロンでかかえてもどってきました。
「おいしい石のスープには、たいがいキャベツがはいってるんだがなあ」
へいたいたちは、にんじんをなべにきっていれながらいいました。
「まあでも、ないものねだりはやめておこう」
「あら、キャベツならさがせばひとつぐらいあるでしょう」
マリーはそういうと、いそいでいえにかえりました。そしてベッドのしたのおしいれから、キャベツを三つもとってきました。
「あとはすこしばかりのぎゅうにくとじゃがいもがあれば、おかねもちのしょくたくにならぶようなスープができるんだがなあ」と、へいたいたちはいいました。
村びとたちは、おかねもちのしよくたくをおもいうかべてみました。
そしてベッドのしたのじゃがいもと、ちかしつにぶらさげたぎゅうにくのことをおもいだして、はしってとりにかえりました。
「おかねもちのスープだってよ。ただの石からだぞ。まるでまほうみてぇじゃねぇか!」
(前掲書)